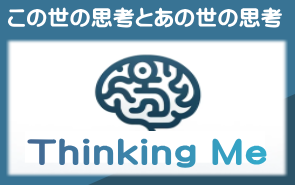小学生 高学年になった君たちへ
思考することの大切さ
こんにちは!毎日が楽しいですか?学校は好きですか?
今日は、『思考』ということについて一緒に考えてみましょう。
学校での授業や日々の暮らしの中で、みなさんはどのようなことを考えていますか?
考えることを『思考』といいますが、それは、単に情報を覚えるだけでなく、それをどう活用するのかを決めるプロセスです。
ここでは、この『思考』が、人生についてどのように作用するのかをみていくことになります。
では、いってみましょう!
自分自身を知るための思考
好きな科目は何でしょうか? 数学の問題を解く時、物語を作る時、音楽のリズムに合わせて歌う時・・・これらのすべてがあなたの『思考』を形作っています。
では、授業以外で一番楽しいと感じる活動は何ですか? ・・様々な活動を通じて、あなたはどのようなことを考え、どのように感じていますか?
学びへの意識と思考
次に、授業を受ける時のあなたの心の持ちようを考えてみましょう。
ただ先生が話すことを聞くだけでなく、その情報をどう使えるかを考えることは、非常に重要です。
どのようにして、その知識をあなたの日常生活や将来に役立てることができるでしょうか?このように考えることこそ、『思考』の力を育て、有意義な満足する人生にしていくことにつながるのです。
現行の義務教育のスタイルと問題点
一律教育の限界
みなさんは学校で同じ教科書を使い、同じ授業を受けていますね。
このような教育システムは、すべての生徒が同じペースで学べるよう設計されていますが、本当にそれがみなさん一人一人に合っているでしょうか?
実は、この一律教育には限界があります。
人によって得意なことや興味があることは違うため、一人ひとりに合わせた学び方ができないことが問題点とされています。
では、何故、問題の多い教育を、長年にわたって行い、変えようとしないのでしょうか?
この問いについての答えは、今のあなた方では、少し難しいかもしれませんが、ここで覚えておいて欲しいのは、”大人の都合” ということです。
こういうと、大人が悪いかのように感じるかもしれませんが、あなたたちが社会に出ると、わかってくると思います。
出来ることなら、なるべく早い段階で、この意味合いを知り、「じゃあどうするか?」と考えて欲しいのです。
これが、ここで身につけて欲しい「思考」なのです。
個性と才能の抑圧
「現在の義務教育では、個々の才能や興味を十分に伸ばす機会が限られていることがあります。
たとえば、数学が得意な生徒も、芸術が得意な生徒も、同じ授業を受けなければなりません。
これにより、自分の才能を十分に伸ばすことが難しい場合があります。
そもそも、才能に気が付くことさえ難しいかもしれません。
こうした弊害をもつ教育制度では、これが原因で学ぶことへの興味を失う生徒もいたりするものです。
学習意欲の低下
全員が同じ教材を使うことで、自分に合わないと感じる生徒は学習意欲を持ち続けられるでしょうか?
授業が自分にとって意味のあるものではないと感じると、学ぶこと自体に対する興味や熱意が減少してしまいませんか?
これは、思考を育てる上で大きな弊害となり得ます。
知識と知恵の違い
知識の役割
学校では多くの知識を学びます。
歴史の事実、数学の公式、科学の原理など、様々な知識を教科書を通じ、先生から学ぶわけです。
そして、時々、正しく覚えられたかについて、「テスト」が行われるわけですね。
覚えた知識を使って、実際にどう考え,行動し,結果どうなって,何を感じたのか・・といった知恵といった部分については、一切触れられませんね。
これらの知識は、世界を理解するための基礎を築くようなものです。
にも拘わらず、今の教育制度では、正確に覚え、教科書通りに答えるのが良いと判断されますね。
知識を覚え、増やすこと自体が目的ではありませんよ。
大切なのは、その知識をどのように使うかということです。
知識を知恵でもって使いこなし、豊かな人生を送れるようになることが大切だとは思いませんか?
知恵への変換
知恵とは、与えられた知識を使って問題を解決したり、新しいアイデアを生み出したりする能力のことです。
たとえば、数学の公式をただ覚えるだけではなく、それを使って実際の生活の中で遭遇する問題を解決することが知恵の使い方です。
知識が情報の集まりなら、知恵はその情報を活かすための能力です。
思考の深化
知恵を深めるためには、与えられた情報について深く考え、自分なりの解釈や応用を見つけ出すことが必要です。
これは、授業で習ったことを日記に書いてみる、または友達と議論をするなど、様々な方法で行うことができます。
知恵は、知識を超えて、自分自身の思考を広げ、人生を豊かにするものです。
感情と人生の質
感情の役割と人生への影響
毎日の暮らしの中で、私たちはさまざまな感情を経験しますね。喜び、悲しみ、驚き、恐れ…これらの感情が人生の質を大きく左右します。
では、感情がどのようにして私たちの行動や決断に影響を与えているのでしょう。
感情は、私たちが何を大切にしているかを示すサインでもあります。
このサインは、どこから来たものか考えてみましょう・・・。
~~~
いかがですか、自分なりの答えが見つかりましたか?
<ちょっと難しい表現になるかもしれませんが、頑張ってついてきてください・・>
あなたたちは、自分の考えを人に伝えるのに「言葉」を使いますよね。
この「言葉」は、あなたが伝えたいことを、そのまま、間違いなく相手に伝えていますか?
~どうでしょうか?意外とそうでなかったりするでしょう?
では、感情はというと、感情は、あなたの心が出したサインですよね。
感情は、「魂の言葉」といってもいいと思います。
感情は、正直ですね、嘘はつきません。
あなたは、この感情を大切にして暮らしているでしょうか?
<このへんで、一休みして、考えてみてください。>
さて、本文に戻りましょう!
感情である、好きなことや楽しいことをするときの喜び、友達との遊びや家族との時間で感じる安心感、これらの感情は、すべて私たちの心にポジティブな影響を与え、充実した人生を送るための重要な要素であるわけです。
感情と思考は、密接に関連しているので、いかに「思考」が大切か、わかっていただけましたか?
自分の感情を理解する
自分の感情を理解することは、自己認識の第一歩です。
自己認識とは、自分がどういう人間なのか理解することです。
どのようなことが自分を幸せにするのか、またどのようなことが不安や悲しみを感じさせるのかを知ることで、より良い選択ができるようになるものです。
たとえば、学校で友達と協力して何かを完成させたとき、達成感や仲間との絆を感じることでしょう。これらの経験からは、「協力する喜び」や「共感する温かさ」を知ることができます。
具体的にどのような事で喜んだのかを知ることは、自分はこんな人間なんだと、知ることが出来るわけです。
感情を通じてより良い未来を
私たちの感情は、未来への道しるべともなります。
自分がどのように感じるかに注目し、それに基づいて行動することで、人生はより豊かなものになるのです。
学校で学ぶことが楽しいと感じるなら、その気持ちを大切にしてさらに学びを深めてみてください。
逆に、何かをすることでストレスを感じるなら、その原因を見極めて、改善する方法を考えることが大切です。
自分の感情を大切にすることで、より満足できる人生を送るためのヒントが見つかるのです。
思考の大切さ
問題解決するための思考
日常生活で直面する多くの問題には、単純な答えがないことが多いものです。
こうした状況では、得られた情報をどのように考え、どのように組み合わせて最適な解決策を見つけるかという『思考』が大切ですね。
例えば、友達とのケンカを解決する場合、感情だけでなく、事実に基づいた冷静な思考が必要となります。
これには、状況となる情報を分析し、異なる視点から状況を判断する思考力が必要となります。
自己反省と成長のための思考
自己反省もまた、豊かな思考から生まれます。
私たちが行った行動の結果を振り返り、それがどのように感情に影響を与えたかを考えることで、自分自身の行動パターンを理解し、将来的により良い選択ができるようになります。
たとえば、テストで失敗した時、その状況をただ悲しむのではなく、何が足りなかったのか、どうすれば改善できるのかといった「思考」が大切です。
創造性を刺激する思考
次は、創造的な思考についてです。
創造的な思考は、私たちに新しい可能性を見せてくれます。
これは学校の芸術の授業だけでなく、科学や数学の問題を解く場合などでも同様です。
例えば、ある数学の問題に対する自分なりの解き方を思いつくことで、それまでとは異なる解答方法を発見するきっかけになったりもするのです。
このような創造的な思考は、今までのやり方を超えて新しいアイデアを生み出す力となり、これが将来の発展につながるのです。
行動の影響
行動が周囲に与える影響
私たちの行動は、自分だけでなく、周囲の人々にも大きな影響を与えるものです。
友達に優しくすることで友情が深まり、教室で積極的に発言することで学びの環境が良くなるなど、小さな行動が積み重なって大きな結果が生まれるのです。
自分の行動が他人にどのような影響を与えるかを考えることは、社会の一員として、よりよく暮らすことが出来るものです。
責任ある行動の重要性
私たちの行動には、常に責任が伴います。
自分の行動が他人に与える影響を考えなかった場合、思わぬ悪影響を与えることもあります。
たとえば、言葉の使い方一つにしても、相手を傷つけるかもしれません。
しっかりとした思考に基づいた、責任ある行動を心がけることは、これを避け、信頼と尊重のある関係を築き、結果、満足できる結果となるものです。
行動が自己評価に与える影響
私たちの行動は、自分自身の自己評価にも大きく影響します。
成功体験や達成感は自信を高め、逆に失敗や挫折は自己疑念を招くことがあります。
失敗から学び、改善することで、より強く、賢く成長することができます。
自分の行動を振り返り、それから学ぶことで、自己評価を向上させることができるのです。
ここでも、思考が強く関わっているのがわかるでしょう。
自分のとった行動を、どう評価するのかは、「思考」そのものなのです。
偏りのない「思考」が出来るように、なっていきましょう。
まとめとメッセージ
人生における思考の役割
これまで、『思考』の重要性と、それが個人の行動や感情、さらには周囲の人々や社会全体に与える影響について考えてきました。
思考は、単に知識を覚えること以上の意味を持ちます。
それは、私たちが直面する課題に対して、どのように反応し、解決策を見つけるかを決定するプロセスです。
思考力の育成とその重要性
日々の学びや経験を通じて、柔軟な思考力を育てることで、より良い人生を送ることが出来るのです。
問題を多角的に見ることができるようになると、より効果的な解決策が見えてきます。
また、思考は創造性を刺激し、新しいアイデアや革新を生み出す源泉となるため、この力を伸ばすことは、満足いく人生を送るうえで、非常に価値があります。
行動と思考の相互作用
私たちの行動一つ一つが、自分自身や他人にどのような影響を与えるかを深く理解することは、責任ある社会人としての基盤を築く上で不可欠です。
自分の行動が引き起こす結果を予測し、その結果に基づいてさらに行動を選択することで、満足する感情を味わうことが出来るのです。
最終メッセージ
最後に、みなさんがこれから成長していく過程で、なるべく早い時期に思考の大切さを理解し、柔軟な思考ができるようになることを願っています。
毎日が新たな発見であり、学びの機会であることを忘れずに、常に好奇心を持って、さまざまなことにチャレンジしてみてください。
思考することは、豊かな人生を送るための土台となります。