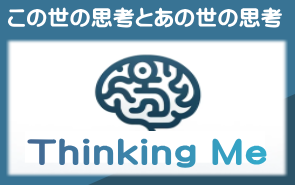第1章:ネガティブ思考に悩んだ日々と思考への目覚め
はじめに|ネガティブ思考だった過去の自分
私が育った家庭は、三世代同居ではあったものの家族間の仲が悪く、特に母が家出を繰り返すような環境でした。幼い私は、常に不安を抱えながら過ごしていたように思います。
その影響か、学校にいても心から笑うという感覚は少なく、周囲となじむことにも苦労しました。中学・高校と進むにつれ「人生とは何か」「どう生きていけばよいのか」と思い悩み、思考は空回りし、心の中は霧がかかったような感覚でした。
定年を過ぎた今、あらためて思い返すと、私はずっと「人生の意味や目的」を探し求めていたのだと思います。その答えを見つけるために、先人たちの書物を読み漁り、目に見えない世界へと思いを巡らせる日々もありました。
学校教育の枠組みでは、記憶と正答が評価される中で、私は「なぜそうなるのか?」と問いを立てることが多く、先生にとっては “めんどくさい生徒” だったかもしれません。そんな風に、私は常に社会や教育の在り方を斜めから見ていたのです。
それでも、小さい頃から好きだった「ものづくり」を活かし、DIYや電気の知識を深め、最終的には電気業界に進みました。電気メーカーの社員として定年まで勤めあげたことは、今では誇らしい人生の一部となっています。
しかし、心のどこかでは常に「もっと気持ちよく、穏やかに生きられないか」と問い続けていたのです。
そうした思考の積み重ねが、私にとっての “救い” でもありました。
家庭環境に恵まれなかったことを背景に、「どうすれば安心して暮らせるのか?」を追い求めた私は、次第に哲学的・精神的な世界に関心を深めていきました。
心理学、精神論、哲学、スピリチュアルなど、さまざまな分野の知見に触れ、自分なりに理解を深める努力を重ねました。
定年を目前にした頃には、人生の “精神的総仕上げ” として、ナポレオン・ヒルの教えをベースにしたコーチング塾に高額な費用を払って参加したり、「思考を整える」ことに特化したグループにも属していました。
そうした時間・お金・エネルギーの自己投資の末、私がたどり着いたシンプルな答えは——
「人生の目的を明確にすること」
目的が明確になれば、自ずと思考のベクトルは整い、人生全体の輪郭がはっきりしてきます。そのことが、私にとっては “救われた” という実感につながったのです。
今この記事を読んでくださっているあなたへ・・
どのようなことも、すべては「思考」から始まります。
思考が言葉になり、言葉が行動になり、行動が現実となって、私たちはその結果を「体験」することになります。
その体験が「愛に近い感情」なのか、「不安に近い感情」なのか。
それによって、人生の質は大きく変わると私は思っています。
あなたは、どちらに近い感情を味わいたいですか?このブログを通して、少しでも「思考の大切さ」が伝われば、私にとってそれが一番の喜びです。
第2章:現代社会とネガティブ思考の関係
なぜ私たちはネガティブ思考になるのか?
現代社会に生きる私たちは、知らず知らずのうちにネガティブな思考に染まりやすい環境に置かれているのではないでしょうか。
まず第一に、人と人とのつながりが非常に希薄になってきていることが挙げられます。かつては当たり前だった大家族や地域社会の支え合いは、今ではすっかり影を潜め、核家族化が進んでいます。
知恵や経験が代々伝わることも難しくなり、たとえば子育て一つとっても、若い夫婦だけで抱え込むケースが増え、不安や孤立感を招いています。
また、経済面でも若い世代を取り巻く状況は厳しくなっています。非正規雇用が増え、安定した生活を築くことが難しくなった結果、「結婚できるだろうか」「将来が見えない」といった漠然とした不安が若者を覆っています。希望が持てない社会では、心が前向きになるのも難しいものです。
私自身の家庭や教育の体験を振り返ってみても、自由な思考を抑圧されてきたと感じることが少なくありません。学校教育では、問いを持つことよりも「正解を覚えること」に重点が置かれてきました。
「なぜそうなるのか?」という問いを発することは、時として教師にとって面倒な存在と映ったのでしょう。個々の考えを述べ合い、他者と対話を通じて思考を深めていくような時間はほとんどありませんでした。
情報環境もまた、私たちを疲弊させる一因です。インターネットやSNSの普及によって、情報は爆発的に増加しました。便利な反面、あまりに情報量が多すぎて「どれが本当なのか分からない」という感覚に陥ることもあります。
特に情報リテラシーが十分でない人にとっては、何を信じ、何を疑うべきか判断するのは容易ではありません。
私自身も、ニュースを見ては違和感を覚えることがあります。とりわけ海外のニュースについて、日本のメディアが報じる内容と、現地の人々が実際に感じていることとの間にズレを感じることが多くあります。
マスコミにも、スポンサーや株主の影響がある以上、報道が“真実”だけを伝えるとは限らないという現実があります。
こうした状況の中で、私たちがネガティブに傾くのは自然なことです。
だからこそ、「情報を選別する思考」や「心を守るための思考整理のスキル」が、ますます重要になってきているとかんじるのです。
第3章:思考を整える実践法
思考整理の3ステップ
ステップ1:感情をそのまま言語化する
私はもやもやした時にはうまく言葉で表現できないことがあります。人と会話している時は「うまく言葉であなたに伝わるかな」と前置きをして、相手が真意を汲み取ろうとする姿勢を引き出すようにしています。
また、自問自答する時などは紙に自分の気持ちを書き出します。文章としてでも構いませんが、私のおすすめは「マインドマップ」で書く方法です。自分の思考の流れが整理されやすく、感情の根本にある思いに気づきやすくなります。
ステップ2:考えと事実を分ける
人間の脳は現実と非現実の区別が難しいと言われています。この脳の特性を思い出すことが大切です。
良い想像であれば、現実でも非現実でも問題ないと感じますが、悪い想像の場合には「これは現実ではない」と自分に言い聞かせることが重要です。私は、悪い想像が浮かんできたとき「キャンセル!キャンセル!」と口に出すようにしています。
このように、現実と想像を区別する習慣を持つことで、思考を整えることができるのです。
ステップ3:自分の価値観とつなげる
私はナポレオン・ヒルのコーチングセミナーや、思考を整えるグループに参加することで「思考の仕方」を意識するようになりました。
その中で出会った仲間たちは皆「自分が思う自分になるため」に努力している方々でした。
また、小川町の有機農業塾でも「食を自分で生み出す」ことに価値を感じている人たちとともに作業をし、安心感や喜びを強く感じました。
価値観に基づいた行動は、心の充足に直結します。
第4章:ネガティブを味方にする考え方
ネガティブな感情が湧いてくるのは仕方のないことです。大切なのは、その感情が出てきたとき「どう考え」「何を言葉にし」「どのように行動するか」です。
ネガティブな体験も、それを通して何を学べるかを意識することで「成長の糧」になります。事実にレッテルを貼っているのは私たち自身であり、物事には本来「良い・悪い」は存在しないとも言えます。
私が尊敬するESP科学研究所の石井普雄先生は「難事は良いこと」と語られていました。その言葉の意味が、ようやく実感として理解できるようになってきました。
ナポレオン・ヒルの教えで印象的だったのは「思考を現実化するには感情の力が必要」ということです。思考だけでは50%、感情が加わってこそ100%なのです。
たとえば「アメリカに行く」という思考に、恋人に会いに行くという強い感情が伴えば、現実化へ向けてすぐに行動が始まります。
このように「思考+感情=現実化」が鍵なのです。
第5章:まとめ|考える力が人生を変える
この記事はいかがだったでしょうか?
私の体験や学びが、読者の皆さんの思考整理の一助になれば幸いです。ぜひ、自分の思考を整え、自分が思う自分になって、人生を笑って締めくくりましょう。
最後に一番伝えたいことは、
「人生の目的を明確にすること」
これを明確にすれば、思考・言葉・行動がその目的に沿っているかを日々確認できます。
そして「明日からできること」として、
- 自分の思考・言葉・行動が目的に沿っているか問いかける
- 目的を達成した自分をイメージしてワクワクする
- その行動の意味や価値を感じながら進む
このようにして、日々のプロセス自体が喜びへと変わっていくのです。
どうか、あなた自身の思考の力を信じてください。そして、その思考を愛と喜びの方向へ育てていってくださいね。